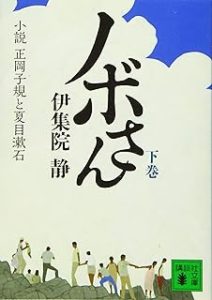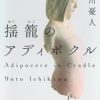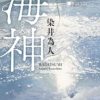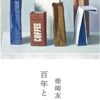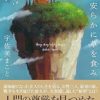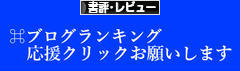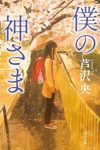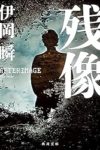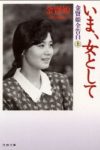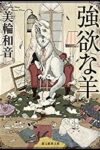『ノボさん/小説 正岡子規と夏目漱石』(伊集院静)_書評という名の読書感想文
公開日:
:
最終更新日:2024/01/13
『ノボさん/小説 正岡子規と夏目漱石』(伊集院静), 伊集院静, 作家別(あ行), 書評(な行)
『ノボさん/小説 正岡子規と夏目漱石』(下巻)伊集院 静 講談社文庫 2016年1月15日第一刷
「シ、キ、と読む。時鳥(ほととぎす)のことじゃ。あしはこの初夏から名前を正岡子規とした。5月の或る夜、血を吐いた。枕元の半紙に血がにじんでおった。それを見た時、時鳥が血を吐くまで鳴いて自分のことを皆に知らしめるように、あしも血を吐くがごとく何かをあらわしてやろうと決めた。それで子規じゃ」(上巻・文中より)
明治28年(1895年)4月、子規は日清戦争の従軍記者として遼東半島に渡ります。新聞社「日本」で働く子規が強く望んで叶った渡航ではあったのですが、既に戦争は終結間際で、唯一従軍中の森鴎外と知り合った以外何ほどのこともなく日本へ戻ることになります。
この帰国の船中で子規はまたも喀血し、神戸に上陸すると、直ちに県立神戸病院に入院します。一時重体に陥り、その後回復して須磨保養院に転院。8月には松山にいる漱石の下宿に移り、50日余りを過ごします。
地元で連日句会を開き(そこには漱石もいます)、10月、子規は松山を離れます。広島から大阪 - そして、そのまま東京へ帰ればいいのに、(随分と体調が悪かったのですが)そこから子規は奈良へと向かいます。
辛かった腰痛が消え、子規は奈良の寺を精力的に見物し、3日かけて東大寺、薬師寺、法隆寺などを散策します。三山以外は起伏のない土地故に景色は実にのんびりとしています。ふと見ると、農家の脇に秋を盛りに無数の柿の木が実をつけています。
子規は久しぶりに一人いて、柿の美しさに目を向けながら散策しています。大陸からの帰り、船中での喀血の時は死をも覚悟し、実際数日間は危篤状態でもあったのですが、何とか乗り越え、松山では漱石に逢い、地元の俳句仲間と語り合ったことなどを思い出しています。
ここに至って、子規は己の身体の限界を思っています。自分がこの先何ができるのかということにおいて、限りがあるのを悟ります。「どうやらあしはこのあたりでおさまりそうぞな」- 奈良での初夜、宿で一人そんなことを思っています。
翌日は体調も良く、子規は法隆寺に向かって歩いています。寺の横の茶屋で昼食を摂るのですが、少しもの足りません。(子規は死ぬ間際まで大食漢だったのです)見ると茶屋の軒から秋の陽に光る柿の実があります。
しかしそれは渋柿で食べられず、代わりに店の老婆が籠に載せた柿を差し出します。ふたつを懐に仕舞い、ひとつをがぶりと食べます。「美味い」- 子規は柿を食べながら歩き、柿を(べーすぼーるの)ボールのようにして投げては受け取り、またがぶりと食べます。
その夜、宿で食事を済ませたあと、子規は部屋の係の若い女に訊ねます。「済まんが、まだ御所柿は食べれぬものかの」- 子規は松山にいる時、御所柿が大の好物でした。若い女は、はい、ございますと白い歯を見せて応え、すぐに部屋を出て行きます。
足音が遠ざかり、また足音がして女が大きなどんぶりに山のように柿を持ってきます。子規は思わず笑い、女も笑って柿をむきはじめます。行燈の薄明りの中、柿のあざやかな朱色とそれを持つ女の透き通った白い肌に、子規はしみじみと見惚れています。
女の差し出した柿を食べ「美味いぞな」と言うと、女は白い歯を見せます。これが何とも可愛く、子規は何やら幸せな気持ちになります。このままこのひとときがずっと続けばいい、と思ったその時、釣鐘を打ったような音がどこからともなく聞こえてきます。
訊くとそれは東大寺の「初夜の鐘」。障子を開けると、秋の月が寺を影にして周囲の木々を照らしています。淋しげな夜の風景 - 女は大仏の御堂の方を指して言います。「夜にはあのあたりに鹿が来て鳴きます」やがて女は部屋を去り、子規は一人で柿を眺めています。
己が今しがたときめいたものと、光る柿の美眺を、昼間見た法隆寺界隈の青空の中の柿と重ね合わせたそのとき、自然とひとつの発句が零れ出します。かの句 -「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」- この発句が完成するのは、それから2ヶ月ほど後のことになります。
・・・・・・・・・・
子規が亡くなったのは35歳、明治35年(1902年)9月19日深夜のことです。
上巻では21歳から28歳までの凡そ7年間、愛媛の田舎町から上京し何か事を成さんとする子規の溌剌とした様子が描かれるのに対し、下巻では一転、病苦に喘ぎながら尚わが道を究めんとする悲愴なまでの子規が描かれています。それもまた7年。長く辛い闘病の日々が見て取れます。
漱石をはじめ、子規の周りには志を同じくする多くの仲間が集まります。彼らは代わる代わる、肉親のようにして子規の世話をします。それはすなわち、子規がそうされるに値する人物である何よりの証しで、彼らは何をも求めず、そうしたいからしているのです。
しかし、忘れてならないのは彼らより尚そばにいて、看病の限りを尽くした母の八重がいて、妹の律がいたことです。子規が息を引き取った矢先、十分にそのことを知りながら、それでも息子の両肩を抱くようにして、冷たくなった子規に八重が声をかけます。
「さあ、もういっぺん痛いと言うておみ」- そう言った時の八重の目には、それまで客たちが一度として見たことのない涙があふれ、娘の律でさえ、母を見ることができずにいます。
この本を読んでみてください係数 85/100
◆伊集院 静
1950年山口県防府市生まれ。本名、西山忠来。日本に帰化前の氏名は、趙忠來(チョ・チュンレ)立教大学文学部日本文学科卒業。
作品 「皐月」「乳房」「受け月」「機関車先生」「ごろごろ」「三年坂」「白秋」「海峡」「春雷」「岬へ」「僕のボールが君に届けば」「羊の目」「少年譜」他多数
関連記事
-
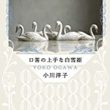
-
『口笛の上手な白雪姫』(小川洋子)_書評という名の読書感想文
『口笛の上手な白雪姫』小川 洋子 幻冬舎文庫 2020年8月10日初版 「大事にし
-
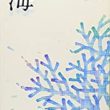
-
『海』(小川洋子)_書評という名の読書感想文
『海』小川 洋子 新潮文庫 2018年7月20日7刷 恋人の家を訪ねた青年が、海か
-
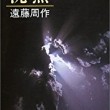
-
『沈黙』(遠藤周作)_書評という名の読書感想文
『沈黙』遠藤 周作 新潮文庫 1981年10月15日発行 島原の乱が鎮圧されて間もないころ、キリシ
-

-
『永い言い訳』(西川美和)_書評という名の読書感想文
『永い言い訳』西川 美和 文芸春秋 2015年2月25日第一刷 長年連れ添った妻・夏子を突然の
-
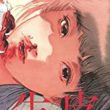
-
『生皮/あるセクシャルハラスメントの光景』(井上荒野)_書評という名の読書感想文
『生皮/あるセクシャルハラスメントの光景』井上 荒野 朝日新聞出版 2022年4月30日第1刷
-
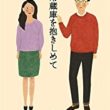
-
『冷蔵庫を抱きしめて』(荻原浩)_書評という名の読書感想文
『冷蔵庫を抱きしめて』荻原 浩 新潮文庫 2017年10月1日発行 幸せなはずの新婚生活で摂食障害
-
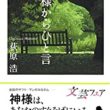
-
『神様からひと言』(荻原浩)_昔わたしが、わざとしたこと
『神様からひと言』荻原 浩 光文社文庫 2020年2月25日43刷 大手広告代理店
-
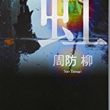
-
『虹』(周防柳)_書評という名の読書感想文
『虹』周防 柳 集英社文庫 2018年3月25日第一刷 二十歳の女子大生が溺死体で発見された。両手
-

-
『その愛の程度』(小野寺史宜)_書評という名の読書感想文
『その愛の程度』小野寺 史宜 講談社文庫 2019年9月13日第1刷 職場の親睦会
-
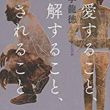
-
『愛すること、理解すること、愛されること』(李龍徳)_書評という名の読書感想文
『愛すること、理解すること、愛されること』李 龍徳 河出書房新社 2018年8月30日初版 謎の死