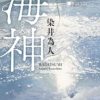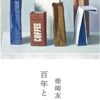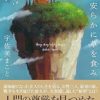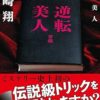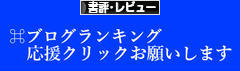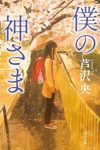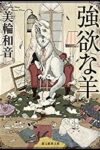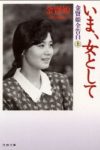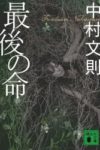『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(辺見じゅん)_書評という名の読書感想文
公開日:
:
最終更新日:2024/01/06
『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(辺見じゅん), 作家別(は行), 書評(さ行), 辺見じゅん
『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』辺見 じゅん 文春文庫 2021年11月5日第23刷
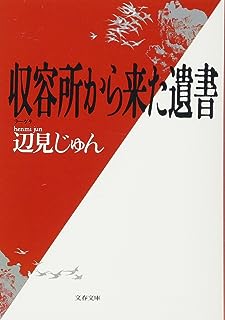
「生きる希望を捨ててはいけません。帰国 (ダモイ) の日は必ずやって来ます」
1945年、零下40度を超える厳冬のシベリアで、捕虜として死と隣り合わせの日々を過ごしながらも、家族を想い、仲間を想い、希望を胸に懸命に生きる男が実在した - 。敗戦から12年目遺族が手にした6通の遺書。ソ連軍に捕われ、極寒と飢餓と重労働のシベリア抑留中に死んだ男のその遺書は、彼を欽慕する仲間の驚くべき方法により厳しいソ連監視網をかい潜ったものだった。悪名高き強制収容所(ラーゲリ)に屈しなかった男達のしたたかな知性と人間性を発掘した大宅賞受賞の感動の傑作。(文春文庫)
世界は矛盾に満ちている。そう思うことが、相も変わらず繰り返されています。地球の環境汚染を声高に叫ぶ一方で、国と国との領土を巡る争いが今も続いています。
そこでは、人が平気で殺されています。真面目なだけの老人が、生まれて間もないおさな子が、ある日突然不幸に見舞われて、生きる命を失くします。それでも戦うことを余儀なくされた青年は、傷を負い病に倒れ、やがて骸となって土へと還るのでした。
本書は、第二次世界大戦の敗戦のあとでシベリア各地の収容所で長い年月を送らねばならなかった日本人捕虜たちの群像を、その一人であった山本幡男の生涯を軸にしながら描いている。これまで断片的にしか伝えられてこなかった収容所での寝起きや労働や食事や学習といったものの実感が過不足なく、端整な筆致でつづられていく。
*
本書に即して言えば、辺見さんが随所で触れている捕虜生活のディテールの描写は、収容所のなかに流れていた時間の感覚に沿っているのではないか、と私は感じる。それはおそろしく緩慢な流れであっただろう。なにしろ敗戦後から十二年間という歳月である。収容所当局の過酷さ、理不尽さ、傲慢さもありふれた日常と感じられるような長さだったのではないだろうか。
せっかちな書き手なら、収容所当局の過酷で理不尽で傲慢な様子を書きたてる。捕虜同士の対立やいさかいを繰り返し書く。だが、それは捕虜たちの実感とは、たぶんずれていくだろう。収容所の日常はそれほど劇的なことに満ちてはいない。
「君達はどんなに辛い日があろうとも、人類の文化創造に参加し、人類の幸福を増進するという進歩的な思想を忘れてはならぬ。偏波で矯激な思想に迷ってはならぬ。どこまでも真面目な、人道に基く自由、博愛、幸福、正義の道を進んで呉れ」 と遺書にしたためる主人公の最後の境地へのみちすじは感動的だが、それがみごとな成熟として読者に感得されるのは、一方におそろしく緩慢な時間の流れがあったからである。
辺見さんはときどきディテールに踏み込むことによって時間の流れを止める。それは捕虜たちの実感を流れていた時間に沿っている、という感じをあたえる。いつまでもつづく、のろのろとした日々の感覚を、こうして読者も共有することになる。
*
そして、それだからこそ、本書の主人公の山本とそのまわりの同じ境遇の捕虜たちが長い、長すぎる年月のあいだに、ゆっくりとだが着実に自分の世界を築いていく様子が、ときにはいたましいまでの手応えとなって伝わってくるのである。
敗戦後にシベリアに抑留された日本人捕虜は、辺見さんも書いているように、六十万人にものぼった。収容所の数は一千二百ヶ所。酷寒と飢えと重労働のせいで亡くなったのは七万人を超える。
そのなかで生き延びるとは、どういうことだったのだろう。どのようにして可能だったのか。本書はそこに、ひとつの光を当てている。(解説より/吉岡忍)
※本作は、映画化が決定しています。2022年公開予定 〇監督 瀬々敬久 〇主演 二宮和也 「珠玉の人間賛歌、心震わす感動巨編」 を、ぜひ映像でも!
この本を読んでみてください係数 85/100
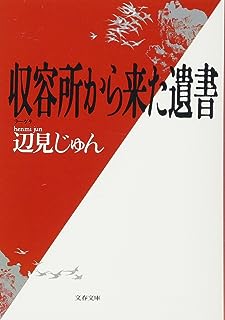
◆辺見 じゅん
1939年富山県中新川郡水橋町(現富山市)生まれ。2011年9月21日逝去。
早稲田大学第二文学部史学専修卒業。
作品 「呪われたシルク・ロード」「男たちの大和」「昭和の遺書」「レクイエム・太平洋戦争」「夢、未だ盡きず」「ダモイ遙かに」他多数
関連記事
-

-
『死にゆく者の祈り』(中山七里)_書評という名の読書感想文
『死にゆく者の祈り』中山 七里 新潮文庫 2022年4月15日2刷 死刑執行直前か
-
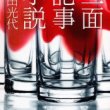
-
『三面記事小説』(角田光代)_書評という名の読書感想文
『三面記事小説』角田 光代 文芸春秋 2007年9月30日第一刷 「愛の巣」:夫が殺した不倫
-

-
『白い部屋で月の歌を』(朱川湊人)_書評という名の読書感想文
『白い部屋で月の歌を』 朱川 湊人 角川ホラー文庫 2003年11月10日初版 第10回日本ホラ
-
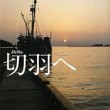
-
『切羽へ』(井上荒野)_書評という名の読書感想文
『切羽へ』井上 荒野 新潮文庫 2010年11月1日発行 かつて炭鉱で栄えた離島で、小学校の養
-
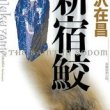
-
『新宿鮫』(大沢在昌)_書評という名の読書感想文(その1)
『新宿鮫』(その1)大沢 在昌 光文社(カッパ・ノベルス) 1990年9月25日初版 『新宿
-

-
『17歳のうた』(坂井希久子)_書評という名の読書感想文
『17歳のうた』坂井 希久子 文春文庫 2019年5月10日第1刷 地方都市で生きる
-
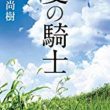
-
『夏の騎士』(百田尚樹)_書評という名の読書感想文
『夏の騎士』百田 尚樹 新潮社 2019年7月20日発行 勇気 - それは人生を切
-
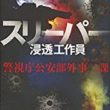
-
『スリーパー/浸透工作員 警視庁公安部外事二課 ソトニ』(竹内明)_書評という名の読書感想文
『スリーパー/浸透工作員 警視庁公安部外事二課 ソトニ』竹内 明 講談社 2017年9月26日第一刷
-
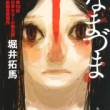
-
『なまづま』(堀井拓馬)_書評という名の読書感想文
『なまづま』堀井 拓馬 角川ホラー文庫 2011年10月25日初版 激臭を放つ粘液に覆われた醜悪
-
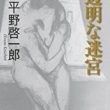
-
『透明な迷宮』(平野啓一郎)_書評という名の読書感想文
『透明な迷宮』平野 啓一郎 新潮文庫 2017年1月1日発行 深夜のブタペストで監禁された初対面の