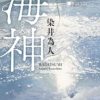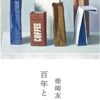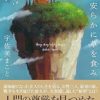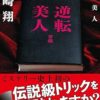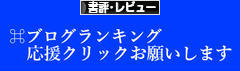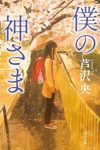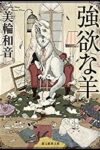『大阪』(岸政彦 柴崎友香)_書評という名の読書感想文
『大阪』岸政彦 柴崎友香 河出書房新社 2021年1月30日初版発行
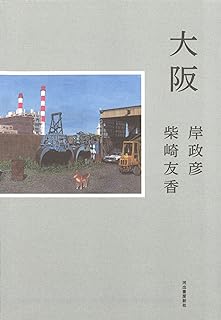
大阪に来た人、大阪を出た人。
かつていた場所と、今いる場所が 「私」 を通して交差する -
『街の人生』 『百年と一日』 の著者たちによる、街と時間の呼吸を活写した、初の共著エッセイ (河出書房新社)私たちはそれぞれ、自分が生まれた街、育った街、やってきた街、働いて酒を飲んでいる街、出ていった街について書いた。私たちは要するに、私たち自身の人生を書いたのだ。(岸政彦)
わかったようなフレーズでは絶対にとらえられないもの、伝わらないことがここにはある。一人一人の生きている時間が、暮らしてきた場所が、確かにある。それをわたしは書きたい。(柴崎友香)「文藝」 連載時より反響を呼んだ、岸政彦さんと柴崎友香さんによる初共著エッセイ 『大阪』。大学生のときに大阪に住みはじめて現在に至る岸さんと、20代後半で生まれ育った大阪を出て東京に住み始めた柴崎さん。おふたりの 「大阪」 への交差する視点は、世間一般で言われがちな 「コテコテ」 「たこ焼き」 「アクが強い」 といった 「大阪」 イメージとは異なる。誰もが知っているけれど知らなかった、大阪の街と、そこに生きる人々が描き出されています。
誰もが持つ、住んでいる/暮らしたことがある土地への思い出。
街のどこか、あのとき、あの場所ですれ違っていたかもしれない、あの人。
『大阪』 は、私たちが生きてきた土地と出会った人々への捨てられない思いを、やわらかく浮かび上がらせてくれるようです。(後略/Web河出より)
アホ言うて笑わしてなんぼや、思てます。「一人でボケて一人でつっこむ」 のは毎度のことで、気にもしてません。たまたま隣にいた見ず知らずのオッちゃんやオバちゃんが、それを聞いて思わずみたいにくすっと笑うと、心で小さくガッツポーズをします。・・・・・・・ ウけたんや、と。
大阪にいるときは当たり前すぎてわからなかったが、東京に来て理解できたこともいくつかある。たとえば、大阪弁は会話を続けるためにある言葉だということだ。(後略)
大阪の人の会話は、意味の伝達よりも、続けること自体に意味がある。大勢の人が寄り集まって生活する中で、潤滑油というか、人と人との摩擦を減らすためにとにかくしゃべることが選ばれた。しゃべり続けている間、自分は怪しくないですよー、と表現しているのだ。
前にラジオで誰かが、この意味のない会話のたとえとして、駅前でばったり会った人に 「どこ行くの? 」 「ちょっと銀行へ」 「強盗ちゃうやろな」 と言い合う光景をあげていた。この先は、いくつも選択肢がある。つっこみの場合 「なんでやねん」、ぼけを重ねる場合 「そやねん、下見に」。ここで相手のほうも、つっこみの場合 「本気やったんかい! 」、ぼける場合 「わしも混ぜてんか」・・・・・・・。
もちろん強盗について話し合いたいわけではないし、特におもしろいことが言いたいわけでもなく、続けたい。せっかく続けるなら笑えるほうがいい、というだけなのです。(柴崎友香 「大阪と大阪、東京とそれ以外」 より)
この一連の会話の “妙” は、おそらく関西以外の人には伝わり難いのではないでしょうか。何をバカバカしいことをと、呆れられるのがオチでしょう。大阪に限らず、関西人が思う会話の理想的なキャッチボールは、他所へ行くと大抵は出来ず仕舞いに終わります。ボケてもボケても空回り、この人何言ってんの? みたいな。
少し真面目な話をしましょう。この本では、あくまで 「大阪」 を論じながらも、二人は交互に、自分自身の人生を語っています。来し方、行く末を語り、何を小説に書き、何を以て研究成果とするか - それらが真摯に綴られています。
例えば、岸政彦先生の場合。大学院生時代に研究仲間とよく行った安い居酒屋の、店を切り盛りする 「夫婦」 の顛末をして、彼が抱いたのはこんな思いでした。
社会全体が自由である、ということは、おそらくほとんどないのではないか、と思っている。たぶん、誰かが自由にしている傍で、誰かが辛い思いをしてその自由を支えているのだろう。そういうことをすべて理解したいと思う。
そして私は今も、週に一度は淀川を歩く。もうあの野良犬の家族には会えないけれども、そして大阪もずいぶんと普通の街になってしまったけれども、それでもやっぱり、淀川を歩くたびに、三十年前に感じたあの自由を思い出すことができる。
三十年前に私ははじめて大阪にやってきて、淀川の河川敷に出会い、大阪の自由を感じた。そして、そこから同じ三十年という時間を遡ると、大阪は、阪急百貨店に子どもが捨てられる街だったのだ。(岸政彦 「淀川の自由」 より)
ここと決めてわざわざ大阪へやって来た人と、住み慣れた大阪からわざわざ出て行った人。二人の思いが 「交差する」 大阪とは、いったいどんなものなのでしょう? 派手なことは何一つ書いてありません。綴られているのは、互いの人生に知らず知らずに沁みついた街の景色とそこで暮らす日々の様子です。
この本を読んでみてください係数 85/100
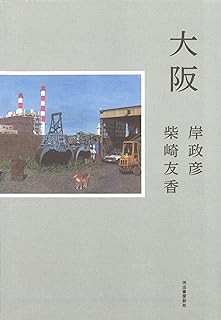
◆岸 政彦
1967年生まれ。
大阪市立大学大学院文学研究科単位取得退学。社会学者。立命館大学大学院教授。
作品 「同化と他者化 - 戦後沖縄の本土就職者たち」「街の人生」「断片的なものの社会学」「ビニール傘」「図書室」他
◆柴崎 友香
1973年大阪府大阪市大正区生まれ。
大阪府立大学総合科学部国際文化コース人文地理学専攻卒業。
作品 「きょうのできごと」「次の駅まで、きみはどんな歌をうたうの?」「青空感傷ツアー」「フルタイムライフ」「寝ても覚めても」「その街の今は」「千の扉」「春の庭」他多数
関連記事
-

-
『文庫版 オジいサン』(京極夏彦)_なにも起きない老後。でも、それがいい。
『文庫版 オジいサン』京極 夏彦 角川文庫 2019年12月25日初版 72歳の益
-
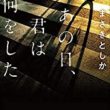
-
『あの日、君は何をした』(まさきとしか)_書評という名の読書感想文
『あの日、君は何をした』まさき としか 小学館文庫 2020年7月12日初版 北関
-

-
『明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち』(山田詠美)_書評という名の読書感想文
『明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち』山田 詠美 幻冬社 2013年2月25日第一刷
-

-
『生きる』(乙川優三郎)_書評という名の読書感想文
『生きる』乙川 優三郎 文春文庫 2005年1月10日第一刷 亡き藩主への忠誠を示す「追腹」を禁じ
-

-
『海の見える理髪店』(荻原浩)_書評という名の読書感想文
『海の見える理髪店』荻原 浩 集英社文庫 2019年5月25日第1刷 第155回直木
-

-
『妖談』(車谷長吉)_書評という名の読書感想文
『妖談』車谷 長吉 文春文庫 2013年7月10日第一刷 ずっとそうなのです。なぜこの人の書
-
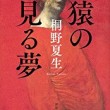
-
『猿の見る夢』(桐野夏生)_書評という名の読書感想文
『猿の見る夢』桐野 夏生 講談社 2016年8月8日第一刷 薄井正明、59歳。元大手銀行勤務で、出
-
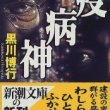
-
『疫病神』(黒川博行)_書評という名の読書感想文
『疫病神』黒川博行 新潮社 1997年3月15日発行 黒川博行の代表的な長編が並ぶ「疫病神シリー
-
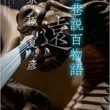
-
『遠巷説百物語』(京極夏彦)_書評という名の読書感想文
『遠巷説百物語』京極 夏彦 角川文庫 2023年2月25日初版発行 物語がほどけ反
-
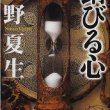
-
『錆びる心』(桐野夏生)_書評という名の読書感想文
『錆びる心』桐野 夏生 文芸春秋 1997年11月20日初版 著者初の短編集。常はえらく長い小