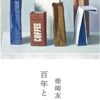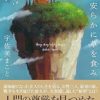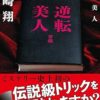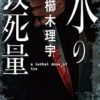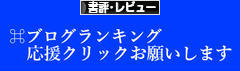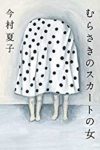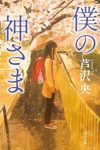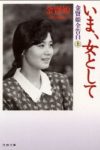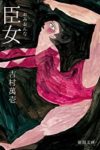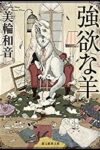『螻蛄(けら)』(黒川博行)_書評という名の読書感想文
公開日:
:
最終更新日:2024/01/13
『螻蛄(けら)』(黒川博行), 作家別(か行), 書評(か行), 黒川博行
『螻蛄(けら)』黒川 博行 新潮社 2009年7月25日発行
信者500万人を擁する伝法宗慧教寺。その宗宝『懐海聖人絵伝』をめぐるスキャンダルに金の匂いを嗅ぎつけた、相性最悪の二人組、自称建設コンサルタントの二宮とイケイケの経済ヤクザの桑原。巨大宗派の蜜に群がる悪党どもは、腐敗刑事、新宿系極道、怪しい画廊の美人経営者。金満坊主から金を分捕るのは誰か。東京まで出張った最凶コンビの命運は? -。(「BOOK」データベースより)
お馴染み「疫病神」シリーズの第4作目。舞台は京都と東京、そして名古屋。3つの都市を行きつ戻りつ、話は進んで行きます。今回は、由緒正しき「お寺」とそこに伝わる大事な大事な「お宝」を巡って繰り広げられる、何とも生臭いお話です。
そもそもは、二宮企画の事務所にいきなりやって来た桑原が、二宮に向かって「就教寺(じゅきょうじ)はおまえの菩提寺か」と訊ねるところから物語は始まります。
菩提寺とは先祖代々のお墓がある寺のことを言います。つまり、おまえの家は就教寺の檀家なのかと桑原は訊ねたわけです。二宮は答えることができません。「おまえ、何宗や」と桑原に訊かれて二宮がした返事は「さぁ、なんやろ。実家の座敷に仏壇があるし、仏教徒であることは確かやけど」という、まるでトンチンカンな、答えにならない答えです。
実は前の年に、二宮の父・孝之の三回忌法要を就教寺でしたばかりなのです。就教寺が伝法宗慧教寺(えきょうじ)派だと聞かされて、ようやく二宮は自分の家が伝法宗であることを思い出します。けだし実家を出て、未だ独り身では仕方のないことかも知れません。
とまあ、そんなことはどうでもよいのですが、桑原が知りたかったのは就教寺の住職である木場博道なる人物が計画したある企てについての現在状況であり、そのために(何の関わりもない)二宮に対して就教寺に行けと言い、木場に会って来いと言います。
では、木場博道が何をしたか - と言いますと、昨年のこと、宗祖懐海(えかい)聖人御誕生800年慶賀法要の記念事業として、宗派宝物の絵巻物『懐海聖人絵伝』を染め抜いた絹のスカーフを信者相手に大々的に売り出そうとしたのでした。
就教寺は伝法宗慧教寺派の管主・仁科家と縁が深く、山内〈六箇寺〉と呼ばれる格式の高い寺院のひとつです。スカーフを作る際、木場は『懐海聖人絵伝』三巻を本山から借り受けています。つまり、本山とは慧教寺のことであり、慧教寺から木場へ貸し出された『懐海聖人絵伝』は宗派で最も大事な宝物である - ということです。
・・・・・・・・・・
ここまでが謂わば事件の発端で、二宮と桑原の最凶コンビが本格的に暴れ出すのは、これから先のことになります。
木場は、『懐海聖人絵伝』が染め抜かれたスカーフを一枚7,000円で10,000枚を売ろうと算段します。しかしその計画は途中で脆くも頓挫し、結果8,000枚が売れ残ってしまいます。スカーフの原価が2,000円、10,000枚の完成品は既に納品された後のことです。
作ったのは、京都の『与志村』という染織屋で、木場は与志村に2,000万円の約束手形を振り出しています。その手形が巡り巡って、二蝶会(桑原の所属する組)に流れてきたというわけです。
手形の取立てを請け負った桑原は、(ただ檀家であるという理由だけで)二宮に就教寺へ行けと言います。木場に会い、まとまった数のスカーフが欲しいと誘いをかけろと言うのです。とりあえず3,000枚。木場は必ず話に乗ってくると桑原は言います。
二宮にはまるで話の先行きが見えません。あれこれ訊ねる二宮に、ビールを飲みながら、桑原は「話は最後まで聞かんかい」と言います。実は桑原には別の意図があり、そのために二宮を利用しようとしています。スカーフのことなど、本当はどうでもいいのです。
桑原の真の目的は、『懐海聖人絵伝』の絵巻物がどこにあるのか、それが知りたいのだと言います。絵巻物は三巻あって、スカーフを作る際に本山から就教寺へ貸し出されているのですが、1年経った今も返却された形跡がなく行方が分からないと言うのです。
「絵巻物が就教寺にあるのなら、本山の坊主が取り戻しに行ったらええやないですか」と言う二宮に対して、「おまえは相変わらずシンプルやのう。貸した巻物を返せ、はい返します、ではわしが出張ることないやろ」と返します。
ここで登場するのが、慧教寺派の管主・仁科家の次男・仁科宜隆(ぎりゅう)なる人物です。宜隆と木場は裏で通じており、木場は多額の金を宜隆に融通しています。では、木場が借金のカタとして宗宝の絵巻物をとったのか? ・・・それが分からないのです。
桑原が目を付けたのは、木場のトラブルや仁科宜隆のスキャンダル - スカーフを餌にそれらを掴めば、必ず金になると桑原は踏んだわけです。このあと、事は桑原の予想をも越えて、本山である慧教寺と、そこに渦巻く利権、また利権へと話が繋がって行きます。
そこへ飛び込んで行くことになる二宮と桑原の二人は、厳かなる仏の世界にはあるまじき、欲に塗れた、俗世でよくある骨肉の争いを垣間見ることになります。
慧教寺は京都・東大路の東、今の地名で言うと今熊野、京都女子大の南にある大名刹で、東京と名古屋、京都・山科等に別院を持ち、全国に6,000の末寺を抱える一大宗教団体です。管主は代々仁科家の世襲で、宜隆は現在、別院の中で最も古い山科別院の住職をしています。
この本を読んでみてください係数 85/100
◆黒川 博行
1949年愛媛県今治市生まれ。6歳の頃に大阪に移り住み、現在大阪府羽曳野市在住。
京都市立芸術大学美術学部彫刻科卒業。妻は日本画家の黒川雅子。
スーパーの社員、高校の美術教師を経て、専業作家。無類のギャンブル好き。
作品 「二度のお別れ」「左手首」「雨に殺せば」「ドアの向こうに」「絵が殺した」「離れ折紙」「疫病神」「国境」「悪果」「文福茶釜」「煙霞」「暗礁」「破門」「後妻業」「勁草」他多数
関連記事
-
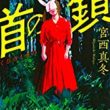
-
『首の鎖』(宮西真冬)_書評という名の読書感想文
『首の鎖』宮西 真冬 講談社文庫 2021年6月15日第1刷 さよなら、家族
-
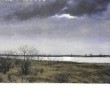
-
『岸辺の旅』(湯本香樹実)_書評という名の読書感想文
『岸辺の旅』湯本 香樹実 文春文庫 2012年8月10日第一刷 きみが三年の間どうしていたか、話し
-
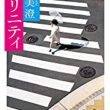
-
『トリニティ』(窪美澄)_書評という名の読書感想文
『トリニティ』窪 美澄 新潮文庫 2021年9月1日発行 織田作之助賞受賞、直木賞
-

-
『侵蝕 壊される家族の記録』(櫛木理宇)_書評という名の読書感想文
『侵蝕 壊される家族の記録』櫛木 理宇 角川ホラー文庫 2016年6月25日初版 ねえ。 このう
-
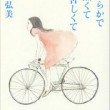
-
『なめらかで熱くて甘苦しくて』(川上弘美)_書評という名の読書感想文
『なめらかで熱くて甘苦しくて』川上 弘美 新潮文庫 2015年8月1日発行 少女の想像の中の奇
-
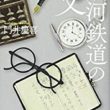
-
『銀河鉄道の父』(門井慶喜)_書評という名の読書感想文
『銀河鉄道の父』門井 慶喜 講談社 2017年9月12日第一刷 第158回直木賞受賞作。 明治2
-
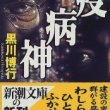
-
『疫病神』(黒川博行)_書評という名の読書感想文
『疫病神』黒川博行 新潮社 1997年3月15日発行 黒川博行の代表的な長編が並ぶ「疫病神シリー
-

-
『ヒーローズ(株)!!! 』(北川恵海)_書評という名の読書感想文
『ヒーローズ(株)!!! 』北川 恵海 メディアワークス文庫 2016年4月23日初版 「なー
-
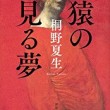
-
『猿の見る夢』(桐野夏生)_書評という名の読書感想文
『猿の見る夢』桐野 夏生 講談社 2016年8月8日第一刷 薄井正明、59歳。元大手銀行勤務で、出
-
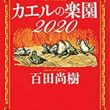
-
『カエルの楽園 2020』(百田尚樹)_書評という名の読書感想文
『カエルの楽園 2020』百田 尚樹 新潮文庫 2020年6月10日発行 コロナ禍