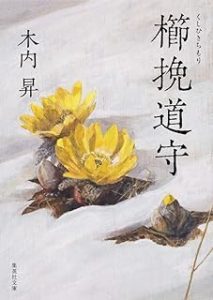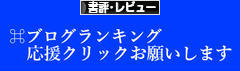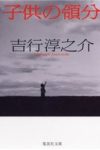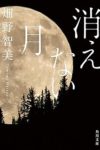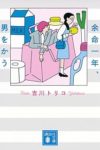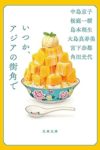『櫛挽道守(くしひきちもり)』(木内昇)_書評という名の読書感想文
公開日:
:
最終更新日:2024/01/12
『櫛挽道守(くしひきちもり)』(木内昇), 作家別(か行), 書評(か行), 木内昇
『櫛挽道守(くしひきちもり)』木内 昇 集英社文庫 2016年11月25日第一刷
幕末の木曽山中。神業と呼ばれるほどの腕を持つ父に憧れ、櫛挽職人を目指す登瀬。しかし女は嫁して子をなし、家を守ることが当たり前の時代、世間は珍妙なものを見るように登瀬の一家と接していた。才がありながら早世した弟、その哀しみを抱えながら、周囲の目に振り回される母親、閉鎖的な土地や家から逃れたい妹、愚直すぎる父親。家族とは、幸せとは・・・・。文学賞3冠の傑作がついに文庫化! (集英社文庫)
余計なことは何も考えない。(読み進むうち)いずれはきっと訪れるであろう際の境地を信じて、ただ一心にページを繰る - それが何より心地いい。
そのとき、私はきっと泣きたいのだろうと思います。今ある全部を忘れて、物語に没頭し、時代を生きた人物らと同じに苦楽を味わい仮の涙を流したいのだと。
思い出すのは、例えば -
『脊梁山脈』(乙川優三郎著)の「多希子」という女性。多希子は、主人公の信幸が復員列車で恩義を受けた康造を訪ね歩く旅中で出会う木地師の娘で、わが身の不幸を不幸とせず、尚清新な心根に思わず胸が熱くなります。
『阿蘭陀西鶴』(朝井まかて著)の「おあい」。おあいは、西鶴の娘。盲目にして、わずか九歳で母を亡くします。死ぬより以前、母はできる限りの家事一切をあおいに教え込みます。彼女は幼くして幾多の要領を得、終生父である西鶴を支えます。
そして、この『櫛挽道守』という物語では、「登瀬」という名の娘が登場します。登瀬は多希子やおあいとはまた違い、時代や慣習に与することなく、あくまで己が信じた父の跡目を継ごうと、克己して櫛を挽く信念の女性として描かれます。
寡黙で一徹な父・吾助がおり、世間体を気にするばかりの母・松枝がいます。妹の喜和は、木曽山中にあるこの藪原宿を、生まれ育ったわが家を、いっときも早く出て行きたいと思っています。
そして、登瀬には三つ下の弟・直助がいます。生まれ持った才があり、父の跡目を継ぐのは当然のように思われていたのですが、その直助が十二になった夏、彼は突然のようにしてこの世を去ります。木曽川の下河原に近い岩の上で、ひっそり死んでいたのでした。
父の吾助が作っているのは、藪原名産の「お六櫛」。お六櫛とは、飾り櫛とも解かし櫛とも異なり、髪や地肌の汚れを梳るのに用いられる櫛をいいます。登瀬の家は代々、お六櫛を挽いて活計(たつき:生計)を立ててきた家です。
梳櫛であるがゆえにとりわけ歯が細かく、たった一寸の幅におよそ三十本も挽かなくてはなりません。髪の毛数本しか通らない狭い歯と歯の間隔を、しかし吾助は板に印をつけもせず、勘だけで均等に梳くことができます。
歯を一本挽き終えると、鋸に添えた左人差し指をかすかに動かし、刃を右に押し出します。それだけで寸分の狂いもなく等しい幅の櫛歯が形作られます。吾助の技に接した誰もが「こんな芸当はとてもできない」と舌を巻きます。吾助の仕事はまさに神業だったのです。
その父の技を、登瀬は何としてもわが技として身に付けようと、作業場である板ノ間に座り続けます。おなごの仕事は飯炊きと櫛磨きで、櫛を挽くのは男の仕事だで - 母に詰られ、妹に呆れられながらも、登瀬は決して吾助の傍から離れようとはしません。
- 父さまは拍子で挽いとるだんね。粒木賊(つぼどくさ)掛けの終わった櫛を、登瀬は人見障子から入る陽にかざしながら、そんなことを考えています。拍子が乱れぬから、当て交いなしでも加減と速さを等しく保って歯が挽けるのだ -
父の仕事を間近に見続けて、それがようやく先頃辿り着いた登瀬なりの答えだったのです。拍子を整えること。等しい拍子を頭ではなく身体で刻めるようになることだ。登瀬もまた父の拍子に合わせて櫛の上に粒木賊を滑らせるのですが、速くてすぐにおいていかれます。ただ櫛を磨いているだけなのに、父の鋸には到底かなわないのでした。
ここら辺りは、まだまだ序盤の話です。この先登瀬が櫛を挽くようになるまでには、気の遠くなるような手間と時間がかかります。その間、妹の喜和には喜和の事情があり、母には母の思惑があります。死んだ弟・直助が書いたという草紙が出て来て、登瀬を驚かせたりもします。
その内ようやく登瀬にも縁談が持ち上がるのですが、登瀬にとっては必ずしも喜ばしい出来事ではありません。むしろしなくて済むならそれがいい、登瀬はそんな心境でいます。しかし、いつしか父の吾助は歳をとり、いかにして跡目を継ぐかが喫緊の問題となります。
「おらの技はよ、おらのものではないだに」- そう言った父・吾助の言葉を、そのとき登瀬は、まだ受け止めきれないでいます。
※ 文学賞3冠:第9回中央公論文芸賞、第27回柴田錬三郎賞、第8回親鸞賞を言います。
この本を読んでみてください係数 85/100
◆木内 昇
1967年東京都生まれ。
中央大学文学部哲学科心理学専攻卒業。
作品 「茗荷谷の猫」「笑い三年、泣き三月」「光炎の人」「漂砂のうたう」他
関連記事
-
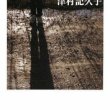
-
『君は永遠にそいつらより若い』(津村記久子)_書評という名の読書感想文
『君は永遠にそいつらより若い』津村 記久子 筑摩書房 2005年11月10日初版 この小説は、津
-
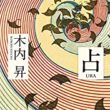
-
『占/URA』(木内昇)_書評という名の読書感想文
『占/URA』木内 昇 新潮文庫 2023年3月1日発行 占いは信じないと思ってい
-

-
『文庫版 オジいサン』(京極夏彦)_なにも起きない老後。でも、それがいい。
『文庫版 オジいサン』京極 夏彦 角川文庫 2019年12月25日初版 72歳の益
-
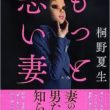
-
『もっと悪い妻』(桐野夏生)_書評という名の読書感想文
『もっと悪い妻』桐野 夏生 文藝春秋 2023年6月30日第1刷発行 「悪い妻」
-

-
『続・ヒーローズ(株)!!! 』(北川恵海)_書評という名の読書感想文
『続・ヒーローズ(株)!!! 』北川 恵海 メディアワークス文庫 2017年4月25日初版 『 ヒ
-
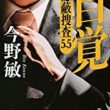
-
『自覚/隠蔽捜査5.5』(今野敏)_書評という名の読書感想文
『自覚/隠蔽捜査5.5』今野 敏 新潮文庫 2017年5月1日発行 以前ほどではないにせよ、時々
-
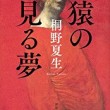
-
『猿の見る夢』(桐野夏生)_書評という名の読書感想文
『猿の見る夢』桐野 夏生 講談社 2016年8月8日第一刷 薄井正明、59歳。元大手銀行勤務で、出
-

-
『カウントダウン』(真梨幸子)_書評という名の読書感想文
『カウントダウン』真梨 幸子 宝島社文庫 2020年6月18日第1刷 半年後までに
-
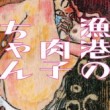
-
『漁港の肉子ちゃん』(西加奈子)_書評という名の読書感想文
『漁港の肉子ちゃん』西 加奈子 幻冬舎文庫 2014年4月10日初版 男にだまされた母・肉子ちゃん
-
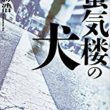
-
『蜃気楼の犬』(呉勝浩)_書評という名の読書感想文
『蜃気楼の犬』呉 勝浩 講談社文庫 2018年5月15日第一刷 県警本部捜査一課の番場は、二回りも